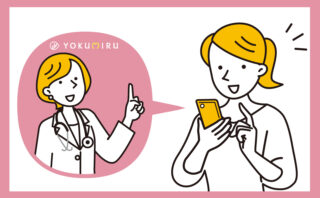自転車大国オランダで暮らして気づいたこと
オランダに来てまず驚くのは、とにかく自転車が多いこと。
今では筆者もほぼ毎日、自転車で移動しています。30分(約10km)くらいなら、バスや電車よりチャリのほうが早いこともよくあるほど。
都市部のアムステルダムやユトレヒトでも、道路には必ず自転車専用道があり、信号のない交差点では車より自転車が優先。感覚的には、
トラム > 自転車 ≧ 歩行者 > 車
こんなヒエラルキーがあるように感じます。
ハウテンってどんな街?

そんな自転車天国のオランダには、都市計画レベルで「自転車ありき」で作られた街があります。
それがユトレヒトの南にある小さな街Houten(ハウテン)。都市デザインの実験場として始まり、いまでは世界中の都市プランナーが視察に訪れるほどの成功例になっています。
自転車都市ってどんな都市プランなのか気になったので、実際に行ってみました。
駅を降りた瞬間から「自転車優先」を実感

ハウテン駅に到着してまず目に入ったのは、駅の真下に広がる巨大な駐輪場(3000台以上!)。しかも改札から直結です。
そして小さな駅にもかかわらず、OV-fiets(貸自転車)が30台近くあったのにも驚きました。

駅を出てすぐに感じたのは「車がいない…」ということ。
駅前には車道が無く、赤い道=自転車専用道、その他=歩行者用。
車が走るアスファルトが見当たらないんです。駅前からすでに「自転車都市」を体感しました。
実験として始まった自転車都市Houten(第1期)

ハウテンの街づくりが始まったのは1970年代。ユトレヒト近郊で新しい住宅地を作る計画として開発された新しい街です。
その際に採用されたのが、車を街の外周に押しやり、自転車と歩行者を中心にした都市計画。
- 車では街を突っ切れず、外周のリング道路をぐるっと回るしかない
- 自転車ならどこへでも直線的にアクセスできる
- 駅・学校・スーパーなど生活に必要な施設は、自転車でサッと行ける距離に配置
結果、「車より自転車のほうが便利」な街ができあがり、自転車利用率が驚異的に高い街に。
まさに自転車都市の実験が成功した例となりました。
成功を発展させたHouten Castellum(第2期)

1990年代、ハウテンの成功を受けて第2の街づくりが始まります。
それが隣町のHouten Castellum(ハウテン・カステルム)で、ハウテンと同様に街の中心部は自転車と歩行者が優先とした都市計画になっています。

ハウテン・カステルムにあるのがSNSでも有名なレインボーハウス(Rainbow Houses)。
Rietplas湖沿いのカラフルな連棟住宅群で、コペンハーゲンの港町にも似た、絵本みたいなかわいらしさがあります。
第2期は、第1期よりも公園や湖を活かした景観デザインが増え、駅周辺の商業エリアも整備。より洗練された暮らしやすさ+オシャレさが感じられる街でした。
緑道とサイクリング体験

ハウテン駅で自転車を借り、ハウテンとハウテン・カステルムを1時間半ほどかけて一周してみました。
- 信号がほとんどなく、車がいないので快適
- 緑道が整備され、どこを走っても並木道が続く
この2点は、どちらの街にも共通した特徴でした。

第1期に作られたハウテンには、「街の構造は枝状で、土地勘がないと迷いやすい」って一面を体感した一方、
第2期のハウテン・カステルムは駅を囲む五角形の緑道があり、「とりあえず直進すれば緑道で、あとはr緑道に沿って走れば迷わない!」という設計になっていて、第1期よりも直感的に走りやすかったです。

1時間半のサイクリングで、すれ違った車はわずか2〜3台。もちろん駐車場もあり、住民が車を所有していないわけではありません。
「車を禁止」ではなく、「車を不便に、自転車を便利に」した街という印象でした。
まとめ:実験が成功した持続可能な街

ハウテンはただの住宅地ではなく、
どうすれば「車に頼らない街」が作れるか?
を実験し、それを実際に成功させた貴重なモデルケース。
その後、ハウテン・カステルムでさらに洗練された持続可能な街づくりが展開され、いまでは世界中の都市デザイナーが参考にする都市計画の代表例になっています。

例えば、街の東西を移動するのに
- 自転車なら直線で10分
- 車だと外周をぐるっと回って10分
不便だけど成立している、不思議な共存。
「自転車が主役の街って、こういう形があるんだ」と肌で感じられる場所でした。