Koninkrijk de Nederlanden(ネーデルラント王国)、首都Amsterdam(アムステルダム)はオランダ最大の都市です。
もともとアムステルダムは小さな漁村でしたが、13世紀にアムステル川に堤防(ダム)を築き、その後は港町として栄えてきました。
アムステル川のダム → アムステルダム
という捻りの無いネーミングですが、今ではヨーロッパ屈指の都市として発展しています。

アムステルダム基礎自治体旗
現在のアムステルダムは、アムステルダム中央駅を中心に市内に網の目状に運河が広がり、その運河沿いには港町として栄え始めた頃からの街並みが今でも大切に残されています。
市内を散策すると、知らず知らずのうちに13〜19世紀の歴史に足を踏み入れています。
アムステルダムの歴史

<photo credit: Google map>
アムステルダムの街並みからは、時代とともに拡張子してきた都市生態が面白いように見て取れます。
観光地であり街の中心 ”セントラル”
セントラルを取り囲む ”運河地区”
環境整備より開拓された ”都市拡張計画区域”
人口増加に伴い展開していく ”ニュータウン”
と、大きく4つの要素に分かれおり、そのエリアごとに整備された時代が異なるように街並みも大きく違っています。
今日は歴史を交えて、アムステルダムを少しご紹介します。
旧市街(セントラル)

<photo credit: Wikipedia>
今では旧市街というと、セントラルとその周りに広がる運河地区も含みますが、元々の港町だったアムステルダムはセントラル部分のみ、現在でのシンゲル川(花市場やムント塔のある川)まででした。
かつてはシンゲル川沿いに町を囲うように壁が建っていました。
現在のアムステルダム中央駅が当時の港に位置し、そこを中心に扇状に市街地が開拓されました。(写真上部がアイ湾とアムステルダム中央駅)
その当時からの町並みの基礎が今でも残っているため、アムスレルダム中央駅からシンゲル川までのエリアの道路は運河に沿うように南北に伸びています。
アムステルダム中央駅からダム広場を通り、花市場までの定番観光ルートが、旧市街になります。
散策の時は13世紀の気分でお楽しみください。
旧市街(運河地区)

<photo credit: Wikipedia>
開拓、干拓、ダム建設、海運貿易と順調に栄えていった16世紀後半からは商業帝国として繁栄し、それに伴い市街地の拡張が大幅に進みました。
現在の旧市街に位置する同心円状の3大運河、
ヘーレン運河(Herengracht)
カイザー運河(Keizersgracht)
プリンセン運河(Prinsengracht)
はこの当時に建設されました。
この運河の建設により市街地は幾何学的に整然とした街区が構成され、アムステルダム独特の街並み、住宅建築群と並木道と運河、という景観都市が形成されました。

<photo credit: Google map>
この当時のアムステルダムの外堀として、もう一つのシンゲル運河が建設されました。それが現在の旧市街の一番外側の運河にあたり、世界遺産にも登録されています。
紛らわしいことにセントラルのシンゲル川(花市場のある川)もまた同じ名前。
Singel(シンゲル)とSingelgracht(シンゲル運河)の運河が付くかの違いだけ。

アムステルダムの古い地図を見てみると、シンゲル運河沿いにデコボコとした城壁で囲まれているのがわかります。
デコボコした部分には風車が一機ずつあったようです。
現在はこれらの城壁も風車も残っていませんが、歴史を知ると町の造りにさらに興味が湧いてきます。
アムステルダムの建築史
続いて建築のお話を少し。

運河沿いの住宅は間口が狭く隣家と接して建設されています。間口は平均5mくらい。狭い家では2mくらいのところもあります。
当時は(現在でも?)間口の広さによって税金がかかるため、間口の狭い家が自然と多いのが特長です。
しかしこれらの家の奥行きは想像以上に長いです。15~20mくらいあるんじゃないでしょうか。旧市街のお店やカフェに入ると奥行きが広くて驚くこともあると思います。
見た目は間口の狭い一軒家に見えますが、アパートだったりと何人もの人が住んでることもあります。
また間口が狭く両隣が隣家と接していることから、間口側と奥側(間口と反対側)には窓がたくさんあります。中には上階から1回まで吹抜けになって採光を取入れてる家も。
オランダの建築法では採光率(室内に入る日光の比率)の規制も厳しく決められているため、室内は決して暗くありません。
この窓の多さがアムステルダムの住宅の特徴の一つです。

またこの窓は引越しにも役立ちます。これらの住宅の階段は狭く急で大きな荷物を運ぶことは不可能です。そのため引越しの時は窓から荷物を搬入します。
建物の破風部分には滑車があり、そこにロープを引っ掛けて荷物を釣り上げます。この昔ながらの方法が今でも使われてるため、たまに街中でこの引越し風景を見かけます。

<photo credit: Wikipedia>
両側が隣の家とくっついていて、前面は道路。一見窮屈そうに感じるかもしれませんが、実はそんなことはないのが上空写真から見ることができます。
旧市街の住宅はドーナツ状に並んでいるため、共用の中庭があることがほとんどなのです。1つのブロックごとに、外周が道路、道路に沿うように家が並び、真ん中部分が緑地になっています。道路側からは全く見えないため、知らない人が多いですし、多分住人以外は中庭に入ることができないのでプライベートガーデンです。しかもその緑地面積も十分で、日本の住宅地にある公園より広いんじゃなかろうかと。
すべての家が公園に面しているかのようになっており、また道路側からは距離もあり、閉ざされているため観光地の喧騒も届きません。賑やかな観光地に住んでいても意外と静かな生活ができるのです。
片側は道路を挟んで運河が見え、片側は大きな緑地 と、市街地に住みながらも自然と隣り合わせの環境です。
アンネフランク美術館のある9ストリート、レストラン街のライツプレインなどが運河地区です。このエリアの区画整備は非常に綺麗なので写真映えします。ぜひともカメラをお供に散策ください。
都市拡張計画区域1

<photo credit: Amsterdam city hall>
アムステルダムの繁栄に陰りが見え始めた18~19世紀には公衆衛生や住宅事情が悪化し、都市環境問題が深刻化となりました。そこで旧市街の外側への都市拡張計画が進み、手始めとしてファン・ニッフトリック案が持ち上がりました。
ファン・ニッフトリック案は公共交通網の整備を主体に公園をふんだんに取り入れ、住宅地と工業地帯を分離する案でした。がしかし、この案が承認されることはありませんでした。
都市計画実施に伴う土地収用や所有権の移転が当時の法規にそぐわなかったのです。

<photo credit: Amsterdam city hall>
それから約10年後に提案されたカリフ案。前案とは正反対的な格子状の道路に住宅が建ち並ぶ合理的な計画です。
この計画は既存の農地の所有権を尊重して計画されたため市参事会の承認を得ることができ、集合住宅が高密度で建設されました。
当時のアムステルダムは住宅不足だったため、このカリフ案は過剰人口の受け皿となりました。しかしそれでも狭い土地に多くの住宅を詰め込むやり方で、かつ建築法も不十分であったため住宅の質は劣っており、また高密度で合理的な計画は、住宅街と大通りとの連携は取れておらず、都市計画と呼べるものではありませんでした。
現在でもこのエリアは複雑で、散策していても迷いやすいです。また旧市街と違い運河のように開けている場所がないのも特徴でしょう。その分、大きな公園が幾つかあり、天気の良い日は多くの人が公園で過ごしています。観光地のミュージアムプレインやアルバートカイプ、アムステルダムウエストはこのエリアに該当します。迷子にならないようにお気をつけください。
都市拡張計画区域2
20世紀に入り住宅法が制定されてから自治体は本気で都市計画に取り組み始めました。アムステルダムに出稼ぎ労働者が増え、住宅不足に陥ったことも要因でした。
ここから初めて建築家が都市計画に積極的に参加されるようになったのです。
アムステルダムの都市計画はオランダ建築家ベルラーヘの手に委ねられることとなりました。しかしこの時も簡単には案が通りませんでした。最初にベルラーヘが立案した計画は13年間放置されたのです。

<photo credit: Amsterdam city hall>
その後改定案を作成したベルラーヘ。悔しさをバネにした力作だったんじゃないかと思います。
その案は計画された街路網、住宅の形状、工夫に富んだオープンスペースと精密で造形的にも美しい見事なプランと賞賛されています。
ベルラーヘは住宅を都市の重要な構成要素と考え、個々の建築と集合住宅群を都市デザインに組み入れる美観形成に力を入れ、最初のシカトされた立案から15年目にしてようやく彼の案は承認されました。努力の賜物です。
しかし残念ながら実行されたのはアムステルダム南郊、Amsterdam-Zuid(ザウド)のみでした。(写真黄色の範囲)
魅力的で美しい住宅地をつくりあげたベルラーヘの都市計画論は新しい計画手法の手本となり、その後もアムステルダムの都市計画の基本となりました。
ベルラーヘの都市計画論
都市計画は住宅配置を基本に土木や建築、公衆衛生、社会学、政治学などを取り入れた総合的かつ科学的なものでなければならない。
従来の単調な土木的発想から脱却し都市日の想像を重視すること。
都市計画の公的役割を明確にし、すべての建築計画はそれに適合するよう許可制とすべき…
この辺りはビジネス街なため観光地ではありませんが、奇抜な近代建築が多いです。私もまだ散策できてないエリアなので、またの機会にご紹介できれば。
ニュータウン

現在アムステルダムに住むオランダ人は50%程度らしく、アムステルダムの人口の半分は移民です。人口の急激な増加もあり、現在では住宅不足、不動産の値上がりも顕著です。そのため人工島などの埋め立て地の開発、アムステルダム北部、西部、東部には多くの集合住宅が現在も建設中です。
ずっとアムステルダムに住んでいるオランダ人の知人は、市街地も含めて8年くらい前と街並みは全然変わってきていると言っていました。旧市街は都市計画法や世界遺産登録などの規定により様変わりすることはありませんが、アムステルダムは今後も発展していくことでしょう。それを近くで見続けられたら面白そうだなと思いました。

今日はアムステルダムの都市計画について、独学の範囲でご紹介しました。
あくまで独学なので誤りなどあっても責任は持てませんのでご了承ください。
参考文献;
◎関西大学 集合住宅”団地”の再生手法に関する技術開発研究 リーフレット
◎土木史研究 第11号 自由投稿論文
◎グーグル検索
読みやすいオランダの歴史本
アムステルダム物語―杭の上の街
緩い地番のアムステルダムが、どのようなプロセスを経て現在の都市へと至ったのか。建物の構法にはいかなる工夫が施されてきたのか。数多くの杭の上に築かれた都市と建築のガイドブックです。
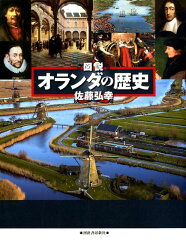
図説 オランダの歴史
低地国土ゆえの水との戦い、スペインへの反乱、大航海時代の光と影など、日本とも縁の深い国オランダの多彩な歴史をまとめた本です。











